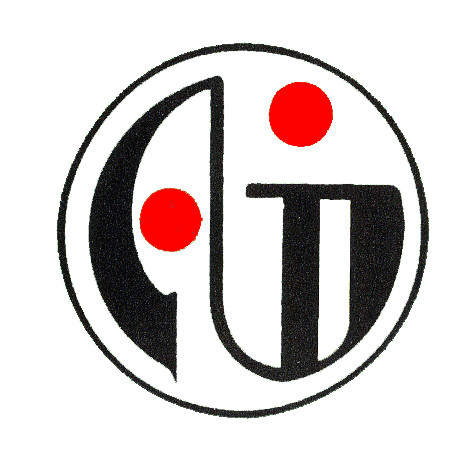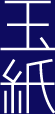
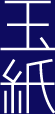

|
−こだわりあるプロ集団におすすめします−
|
|
|
「玉紙は、従来の問題点を解決した和紙壁紙の決定版!」
|
|
|
〈従来品の問題点〉
|
〈問題解決型商品「玉紙」〉
|
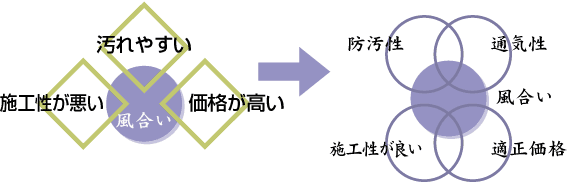 |
|
| 従来和紙の場合 | 一般のビニールクロスの場合 |
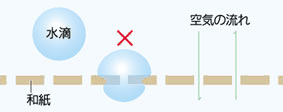 |
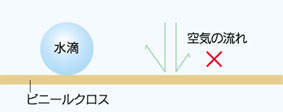 |
|
|
|
|
玉紙のしくみ
|
|
 |
|
| 1.ケチャップを貼付した場合 | |||||||||||
|
|
||||||||||
| 2.しょう油を貼付した場合 | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
撥水・防汚などの機能性
|
水
|
コーヒー
|
醤油・水性ペン
|
クレヨン
|
通気性
|
|
超撥水和紙壁紙 玉紙
|
◎
|
◎
|
○
|
△
|
◎
|
|
和 紙
|
×
|
×
|
×
|
×
|
◎
|
|
一般のビニールクロス
|
◎
|
○
|
○
|
△
|
×
|
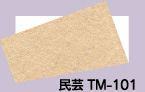 |
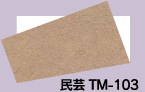 |
 |
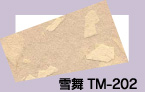 |
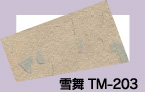 |
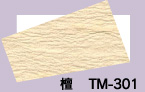 |
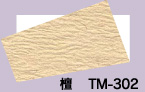 |
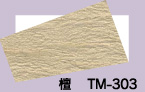 |
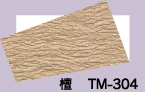 |
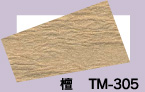 |
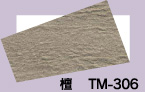 |
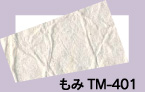 |
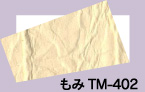 |
 |
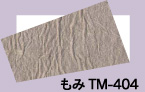 |
| 和紙の歴史は古く古代中国で発明され、中央アジアを通じ朝鮮半島を伝播しながら、日本には高句麗の僧曇徴が伝えたと言う記録が残っています。 日本で作られはじめたのは飛鳥時代で、大宝律令の後です。日本で最古の紙は美濃・筑前・豊前で、奈良時代に入ると、楮紙・雁皮紙のほか、植物からとった染料を使った染紙など、装飾を施した紙も作られるようになりました。 その後に国風文化が起こり、平安時代にかけて最も高度な技術が集まりました。その様子は日本書紀にも、和紙に関する記事が残されています。 また、和紙は欧米で高く評価され、輸出されるようになりました。しかし、大量生産される洋紙が普及し、和紙は工芸的な用途や、趣味にのみ使用されるようになりました。 近年はこうした流れを背景にして、和紙の美しさや価値を見直されており、さらに素材を生かすものが注目されるようになりました。 |
三椏(ミツマタ)の花  |
楮(コウゾ) 桑科の植物。栽培が比較的容易なため和紙の産地では、どこでも栽培されている。主産地は高知や茨城などです。 太くて強靱な楮の繊維で漉かれた紙は、男性的な風合いを持っています。古代には楮紙は穀紙といわれていました。 三椏(ミツマタ) 雁皮と同じジンチョウゲ科に属し、枝は三又に分かれているのが特長です。栽培が可能で、高知、徳島、愛媛の四国地方や、岡山、島根などの中国地方が生産地です。三椏紙は紙肌がきめ細やかで、柔軟性に富み、光沢もあって和紙の女性的な代表といえます。 雁皮(ガンピ) ジンチョウゲ科に属し、やせた土地などに自生しています。生育はきわめて遅く、栽培は難しい。三重、和歌山、兵庫、高知などが主産地です。 雁皮の繊維は細かく均等で、繊維自体に光沢があり、強靱で虫害にかかりにくい。そのため雁皮紙は独特な光沢をもち、緻密で、肌がなめらか、しかも、耐久性に優れているので「紙の王様」と称えられています。 また、色が鶏卵の殻の色に似ていることから「鳥の子」の名で親しまれています。古くは斐紙(ひし)といわれていました。 |
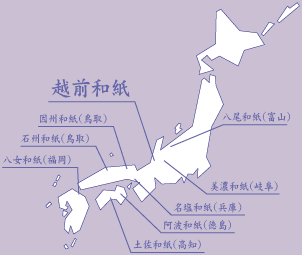 |
1500年の歴史と 伝統を誇る越前和紙 福井県今立町(最寄りは武生駅鯖江駅武生インター)に五箇と呼ばれる、大滝・岩本・不老・定友・新在家の五集落が、手すき和紙の生産全国一を誇る越前和紙の里である。冬、山あいのここは屋根まで雪に埋もれます。 |
| その歴史を尋ねると、今からおよそ1500年ほど前に継体天皇が皇子の頃その寵姫・川上御前が現在の福井県今立町の里人に紙漉きの技を教えたと伝えられています。それ以降、奈良時代になると仏教が盛んになり多くの寺が写経の為に越前和紙を求めたと言われております。 鎌倉時代には、今立の地に勢力を誇っていた大滝寺の保護を受けて紙座(組合)が設けられ、1338年に守護大名である斯波高経(しばたかつね)が紙座の長、道西掃部(どうさいかもん)に献上させた紙の評判が高く、「出世奉書」と命名され、室町時代には奉書紙等の需要が高まる中、「越前奉書」として高い評価を受け全国に発展します。 以来、越前和紙は公家、武家の公用紙として普及し、確固たる地位を築き、明治時代に入ると様々な改良が加えられ、紙幣製造や横山大観をはじめとする多くの芸術家の指示を得て全国にその名を知られるようになりました。そして、現在も数ある和紙の中で品質・種類・量とともに日本一の存在となっております。 |
|